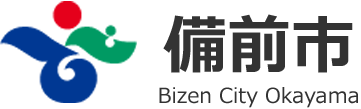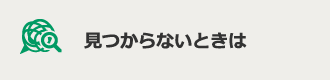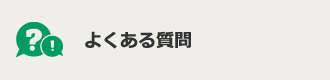本文
避難行動要支援者登録制度・個別避難計画
避難行動要支援者登録制度
避難行動要支援者登録制度とは
避避難行動要支援者登録制度とは、水害や地震などの災害が起こったとき、自ら避難することが困難で、家族などの支援が十分に受けられず何らかの助けを必要とする方(避難行動要支援者といいます)を支援するための制度です。
避難行動要支援者として、事前に登録することで、日ごろから、地域の避難支援等関係者が、避難行動要支援者を把握しておき、災害が発生した場合に、地域の助け合いによって、少しでも被害を減らそうとすることがこの制度の目的です。
避難行動要支援者とは
災害が起こった時に自分の力で避難することが困難な人をいいます。
避難支援等関係者とは
避難支援等関係者とは、災害発生時に避難行動要支援者の避難支援などに携わる方で、市内の警察、消防(団)、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地元自主防災組織(地元区会、町内会)です。
避難行動要支援者名簿とは
避難行動要支援者が、事前に登録した方の名簿をいいます。市では、水害や地震などの災害発生時に、自分の力で避難することが困難な人について、申請に基づいて、避難行動要支援者名簿を作成します。
作成した名簿は
市に提出された登録申請(同意)書に基づき、同意のあった方の避難行動要支援者名簿を作成します。作成した名簿は、市内の警察、消防(団)、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地元自主防災組織(地元区会、町内会)へ平常時から名簿を提供し、災害発生時の安否確認や避難する際の支援などに使用します。
なお、この名簿の情報は、目的以外のことには一切使用しません。
登録できる人
災害が起こった時に自分の力で避難することが困難な人で、避難するために何らかの手助けが必要となる人です。ただし、施設に入っている人や長期に入院している人は、登録できません。
- 一人暮らしの高齢の方
- 介護保険の認定を受けている方
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
- 難病のある方
- 上記以外で、自ら避難することが困難な方
注意事項とお願い
災害の状況によっては、避難支援に携わる方(避難支援等関係者)も被災者となることもあります。登録したからといって、必ずしも災害時に支援が受けられるとは限りません。日頃から近所の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。
また、自分の身は自分で守るという心構えと災害への備えも忘れないようにしてください。
支援を希望する人はまず登録を
災害時において支援を希望する人は、備前市避難行動要支援者登録申請(同意)書を、各申請窓口まで提出してください。
申請先(問合せ先)
下記区分に該当の申請窓口へ申し込んでください。
| 区分 | 申請窓口 |
|---|---|
| (1) 一人暮らしの高齢の方 | 社会福祉課地域福祉係(Tel64-1827) |
| (2) 介護保険の認定を受けている方 | 介護福祉課介護保険係(Tel64-1828) |
| (3) 身体障がい害者手帳、療育手帳、 精神保健福祉手帳をお持ちの方 |
社会福祉課障がい者福祉係(Tel64-1824) |
| (4) 難病のある方 | |
| (5) 上記以外で、自ら避難することが困難な方 | こどもまんなか課相談係(Tel64-1853) 地域包括支援センター(Tel64-1844) 東サブセンター(日生総合支所内Tel72-1240) 北サブセンター(吉永総合保健施設内Tel84-9114) |
個別避難計画
個別避難計画とは
個別避難計画とは、高齢者や障がいのある方(要配慮者)などに、自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに作成する避難支援のための計画となります。
過去の自然災害で避難行動要支援者に被害が多くみられることを受けて、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画を作成に努めることが法律に位置付けられました。
個別避難計画の作成
個別避難計画は、避難行動要支援者ごとに、支援等実施者、避難先、避難方法、配慮すべき事項などをあらかじめ定めておくことで、速やかに避難支援等を行うことを目的としています。
個別避難計画の作成にあたっては、行政だけでなく、区会・町内会・自主防災組織や民生委員児童委員、福祉・医療・保健の専門職などの関係者が連携して作成します。
- 個別避難計画について [PDFファイル/170KB]
- 個別避難計画 様式 [Excelファイル/31KB]
- 個別避難計画作成マニュアル(岡山県)https://www.pref.okayama.jp/page/911995.html<外部リンク>