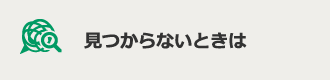本文
備前焼の生い立ち(4/7)
桃山時代の美意識と備前焼
美意識改革推進の旗手
室町時代末期、さらに引き続いてやってきた桃山時代は、長く展開された戦国時代の終結と、安堵からくる見通しとゆとりを手に入れ、また地理的世界の広がりと並行して日本人の中に南蛮文化とキリスト教による物理的な新しい世界との交流の中で、また精神的世界の広がり、また新しい世界観や美意識など価値観の多様化が起こり、自己と全体と、何より人間を見つめ、既成の美意識に挑戦するという魅力的な時代の始まりでした。
多様性と自由な世界観を背景として、文化的に最も大輪の花を咲かせた時代です。
それはこの時代は日本の歴史の中では、不思議な雰囲気を持ち、何かの始まりを告げる新しい時代でもありました。文化的価値の見直しが行われたわけです。
そのような時代に経済原理の法則のままに進出した備前焼は、さらにどのように変化を見せていくのでしょうか。
千利休、古田織部などの茶人はその時、それまでまかり通ってきた美に対してのアンチテーゼと自分の美意識の理論構築の実証手段に備前焼を、粗野ではあるが不思議な力を持っているものとして取り上げたのです。それは矛盾の中から新しいものを生もうとする考えと、見通しを持てることからくる考え方の余裕と自由な感覚のさらなる拡大ではなかったでしょうか。それは完璧な中国陶磁器至上主義にとらわれていたものからの解放でもありました。
そこから人間臭さの存在と人間の手の介在しない自然の力、神秘の力の介在、そこに宇宙を、心を、人間と自分と、ものの哀れを感じるようになったのです。下剋上の戦争に明け暮れて死んで行った人達、手足をもがれるような大怪我をした人達、諸々の姿で生死をさまよった人達はそれまでの勝ち優先の通念では全く意味のない、光の当たらなかった陰の部分の人達だったけれど、立ち止まることの中から、その者にも光を当て、意味を見つけ、並行して焼物であれば、ねじれたり、裂けたようなものにもう一度改めて光を当てる心の幅を持つようになったのです。現実には価値観のさらなる多様化が始まっていくわけです。
利休といえども、先駆けとして村田珠光(1422〜1502)がいなければ、美意識の改革と体系化は不可能だったかも知れません。社会的矛盾、たぐい希な人物の登場、時代が見通せる武将、見通しに沿った時代の接近、こうした環境が利休のそばにあったと思います。
ほれぼれする美しさ
村田珠光『秘伝書(1480)』の中で、「初心の人躰が、ひぜん、しがらき物などを持ちて言語道断也」と記しているが、それはもう新しい美の発見とその感動の虜になっていたことがよく分かります。彼が生きていた世は戦乱に明け暮れ、また一方で明や琉球を通じ次第にもっと広い外にも目が向いていく中で、彼のような敏感なごく一部の人間は新しい価値観について模索していたのでしょう。それが、利休、織部などによって体系づけられたのです。
まさに心の自由に関するもの、心象芸術の領域に三次元物が踏み込んでいくようなものでした。日本人の生活の中で焼物の使い方、見方の幅をこれほどまでに広げたのも備前焼の存在があったからかも知れません。
蛇足ながら、先の見通しがよりはっきりと立ってくると、秀吉という支配者側からすれば、美とはそうした実用的で粗野なモノも受け入れるけれども、次第に逆行と思われる豪華絢爛も美であると受け止めてくるようになってきました。一方の極を知ったから余計に秀吉は自分で違った対局の奥を真の意味で探りたいと思ったのかも知れません。
しかし利休とか織部といった、そういった自由な人間は、そういう絢爛たる美が本当に日本の美ではないのだとますます異議を唱えることになります。これまで自ら構築した美意識の上に結晶を作ろうとしたし、自由な雰囲気は当初にはそれを許したが、やがて利休は秀吉によって自決に追い込まれるというすさまじい対決を余儀なくされてしまいます。ただ当時庶民が時代の最高権力者と堂々と対決できたこと自体、これまでにない自由の時代であったのかも知れません。
ともあれ、そういう新しい時代を担う識者の心情と一番共鳴しやすい美を備えた焼物が備前焼だったわけです。
つまりモノからすれば、備前焼は利久たちの進める、日本における時代の転換期の美意識の改革推進の旗手となったともいえるのです。
このことは岡山県人にはあまり理解されていません。日本の美術史の中で備前焼は意外なほど大きな役割を果たしたことになりますし、焼物自身もそれをはっきり感じていたようです。
ですからその時代の備前焼というのは驚くほど美しい。現在のように誇張したり、あるいは手を加えたりすることを必要とせず、偶然の美しさをあるがままにフルに引き出しているわけです。放っておいても力を放っているではありませんか。桃山備前は万人の心をとらえて離さない新しく生まれ行く文化へのときめきのようなものを備えていました。
桃山時代がさらに時間的経過を重ねていくと、やがてその備前焼は単なる素朴さや個人的好みを離れて、素朴さを美的作為である芸術にまで、見つめられることによって、昇華させていきました。
決して、現代を含めてその時代以外の者が真似をしても、真似のできるものではありません。それが時代の「勢い」であり、「精華」であり、洗練され切った「瀟洒」であります。
後の時代の誰も乗り越えられない、ほれぼれする美しさを持っています。
つまり現代の作家が桃山備前以上のものを作れないのは、社会全般の時代を受け止める感覚や美意識において、当時に比べて乗り越えていない部分が大きいからではないでしょうか。私は謙虚に、当時の庶民や作る人、時代を動かす人達の美意識や審美眼を私たちの時代の人間が超えているとは思えないのです。
茶陶として軍需品として
そうした文化として固定されたものを見てみますと、心色の豊かさにあふれています。そうした中で茶の湯の隆盛も極に達しました。備前焼は物質的広がりの対極をなす精神的、心象的美を具備固定化しているものとして、またもてはやされました。
また茶の湯の中で、備前が第一に取り上げられた時代でもありました。
「わび・さび」という茶道の感性の中で、媚びたり飾ったりすることなしに、ひたすら実用品に徹してきた備前が、一躍茶道具として認められたのです。
茶人はこよなく備前焼を愛でたのです。使うことに徹した姿勢が、心象芸術としての洗練も、自然に高めていったのです。
秀吉は備前焼に大変執着しています。何故彼はこれほどこだわっていたかについては、軍事戦略上の理由がもう一つありました。信長から引き続いて全国制覇を推進する中で、大きな抵抗に直面した城や寺社ではほとんどすべて備前焼の大甕などを備えて篭城していることを思い知らされていたので、備前焼の恐ろしさは秀吉の脳裏から離れることはなかったはずです。
秀吉は中国筋遠征の途中、つまり天正10(1582)年に備中高松城水攻めの際伊部に立ち寄り、『伊部の里陣地に関する制札(伊部村陣執禁止)』を出しています。
いわゆる秀吉の「備前焼の保護策」といわれているもので、燃料、原土の無料政策を打ち出しています。実はこれは篭城に役立つ備前焼の恐ろしさを知っていた上で、これを手中に納めるべく取った彼の懐柔手段なのです。
また名高い天正15年の北野の大茶会には、「紹鴎の備前水こぼし、備前筒花入」等を飾ったことが記録されています。この段階で、秀吉の得意満面の顔が見えるようです。
続いて天正15(1587)年には、秀吉が備前窯を1ヶ所にまとめるとの記述が「平塚山城守書状」に見られ、秀吉による備前焼支配が一段となされているのです。そして死期に至ってもなお備前焼に対する安心感と経済的恐れを持ち続けていたことは、慶長3(1598)年備前三石入大甕に入って京都東山の豊国廟に葬らせることに端的に現れています。秀吉にとって備前焼は生活必需品、精神的美の創造物のみならず、根底には軍需品に映っていたに違いないと思います。
しかし無限に続くと思われていた「洗練」は意外な形で終焉を迎えました。
続く平和な都市生活を形成した江戸時代を迎えて、表面上繊細で奇麗な伊万里などの釉薬物に押され、備前焼は音無しの構えで、昭和になるまで鳴りをひそめて眠りこけてしまったのです。
精神やそれに基づく心象芸術ではなく、人間業の領域の占める、美しくて、軽やかで、繊細なものに誰もが憧れはじめ、反面備前焼は衰退の一途をたどっていきました。その時代にさらなる完成者がいなかったのか、備前焼上での洗練はこれより上のない絶頂であったのか、時代がすり替えてしまったのか、首座は交代してしまったのです。