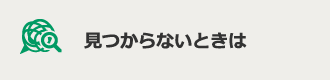本文
備前焼の生い立ち(2/7)
鎌倉時代の備前焼
光りが差しはじめる
世界最大の木造建築東大寺は治承4(1180)年平清盛の子平重衡によって焼かれました。
東大寺再建に要する費用は、当初から平氏ゆかりの播磨、備前、周防からの収税が当てられたのです。再建に当たって、かつて中国に渡って幅広い学問を修めていた僧重源(1121〜1206)の果たした功績は多方面で大きかったのです。
財政的費用、労働、資材等を負担した代わりに、彼はこれらの土地に造寺、造仏、湯屋、土木工事等新しい文化や施設、技術をその地域に導入して報いたのでした。そこに窯業に関する技術指導があったとしても不思議はありません。
建久4(1193)年の再建東大寺の屋根瓦は、東大寺領であった備前国の万富で9割以上が焼かれ、備前焼の近くや、吉井川河口の福岡を経由して舟で奈良へと運ばれました。残りの数パーセントが渥美の伊良湖で焼かれました。ともかくも窯業再建への大きな光が備前に差し始めたのです。
符丁を合わせたように、このころ各地の出土品や絵巻などにも備前焼が現れ始めます。その時代の風俗をきわめて正確に描写していることで有名な『一遍上人聖絵』を見ると、当時西国筋で最大の都市であった備前福岡(九州福岡の地名のルーツで、慶長6(1601)年に命名)のマーケットにも備前焼が商品として、また、他の商品を入れる器として登場しています。
この絵伝は一遍の死後その善行を記録に残す目的で正安元(1299)年に描かれました。
しかし依然として備前は大勢として酸化焼成には至らず、どちらかというとなお暗い灰色のものが大半を占めていましたが、それでも近隣を中心に販路を広げていったらしく、この頃から広島県東部の草戸千軒などに出土例が次第に多くなってきました。しかし鎌倉末期から室町期になると、片上港が瀬戸内海のほぼ中央に位置する重要港として栄え、山陽道も三石から瀬戸へ抜けるコースから、伊部、福岡を通るルートに変わり、片上と福岡が大いに繁栄し、販路の拡大とともに、経済環境はみるみる立ち上がり始めました。
窯の規模もそれに応じて大型化に向かい、平安末期から鎌倉初期にかけて、渥美、常滑、加賀、越前、信楽、丹波などの他の日本の中世古窯の面々に完全に後塵を拝して冴えなかった備前焼の表情も、やっと酸化焔焼成に変わり始め、赤い発色をするものになっていきました。
この冷たい試練の時代の谷間でも火を消すことはありませんでした。
室町時代の備前焼
全国の市場を制圧
南北朝時代から、室町時代初期にかけて、備前焼は力をつけて戻ってきました。一旦へこたれた備前の焼物が立ち上がるのは、このようにかなりの時間を要しました。
備前焼はすっかり感覚や指向を変え、衣替えして全国シェア拡大に向けて大進撃を開始しました。それだけではなく、甕、壷、摺鉢の製品のいずれもが、実用性、耐久性において他を圧倒し首座を占めていくのでした。とりわけ巨大な三石入大甕や、摺っても摩滅しない摺鉢を中心に生産を伸ばし、庶民の支持において他の追随を許さない程になりました。
その頃の都市に住む人々の台所では、備前焼無しでは日々の生活が成立ち得なかったようです。水甕を取り上げても、「備前の水甕、水が腐らん」と言われていました。
備前の水甕は水が腐らない、という言い伝えは嘘ではありません。
日本の他の中世の古窯に比較して、備前焼は最も焼成温度が低く、かつ最も長時間焼いた焼物でありました。やはり無理をせず、素材を殺さず、積算温度は十分に確保して、硬く、しかも歪ませなかったために、長所を存分に引き出すことが出来たのです。そのため他では真似の出来ない巨大な三石入大甕も焼き上げることが可能となったが故に山城用、醸造用、都市生活用として渇望され、全国の市場を制圧することができました。
実際、無釉で厚みもあり、また高温で焼いていないためもあって器面がつぶれておらず、内側の表面積の大きさは抜群で、またかすかな浸透性もあり、外面における気化熱の作用で外気温が高ければ高いほど中は冷え、甕は楽に呼吸しながら中味も生き続け水が腐らない理由になっていたのです。
次に、摺鉢についても、「備前の摺鉢投げても壊れん」という言葉通り強く、硬いために使い込んでも摺り目が減らない極上品であったようです。多量生産に向くように、窯の中で重ね焼きしても、溶着しない口縁部形状の工夫も備前で初めて完成しました。昭和52年に小豆島沖の海底から引き上げられた、189点にのぼる多数の備前焼は、船荷として遠方へ輸送されていたことを物語っています。
それを裏付けるように全国の考古学的な発掘が進む中で、数々の備前焼が報告されるようになり、その流通領域が次第に明らかになってきました。
私は昭和54年、当時わが国ではじめて備前焼の流通の実態を面的に明らかにしました。その時は備前焼の出土する中世遺跡は全国で300箇所を数え、その広がりの限界は西の種子島から、東の千葉県鎌ヶ谷市満福寺遺跡でありました。
今はさらにデータは集積され、その広がりは、西は沖縄今帰仁城遺跡から東は埼玉県針ヶ谷まで確認しています。江戸初期に至ってはもちろん北海道(勝山遺跡)まで到達しています。国内の焼物市場制覇へ向けた凄い力が浮き彫りにされているのです。
昭和39年(1964)に発見された古文書『兵庫北関入舩納帳』は、現在の神戸港に相当する兵庫北関に入港する船や船籍、問丸、積荷や通関税に至るまで詳しく記した帳簿でした。しかも1年間にわたって丹念に記帳されていたことから、中世半ば、室町初期の瀬戸内の商品流通はもとより、日本の海運、経済を如実に物語る一級資料だったのです。
この古文書により、記録の上からも備前焼の流通の実態が裏付けられてきました。
この資料は読めば読むほど、色々な情報をわれわれに提供してくれる不思議な魅力を持っています。
記録からもこの時代は実に色々な商品が京畿に向かって活発に動いている様子がよく分かります。
| 【月別(旧暦)備前焼荷揚げ数】 (カッコ内は備前以外の焼物点数) |
||
|---|---|---|
| 正月 | 0個 | |
| 2月 | 0個 | |
| 3月 | 0個 | |
| 4月 | 0個 | |
| 5月 | 0個 | |
| 6月 | 200個 | |
| 7月 | 180個 | |
| 8月 | 285個 | (40) |
| 9月 | 330個 | (100) |
| 10月 | 60個 | |
| 11月 | 170個 | (50) |
| 12月 | 40個 | |
| 合計 1,265個 | (190) | |
この岡山県南部近辺だけでも、今でこそ珍しいが当時は普通にあったらしく、赤米(連島)も商品だったことが分かりますし、フク干物(下津井)、塩鯛(牛窓、笠岡)、塩(塩飽)、マメ(瀬戸田)、米、クラゲ(番田)、材木(甲浦)、大麦、材木(牛窓)、カニ(連島)、ツホ、苧(伊部)、金(瀬戸田、尾道)、鉄(郡)、松(室)、新米(尼崎)、ナマコ(坂越、網干、日那志(日生))などの産物移動の豊かさに驚かされます。米は10月頃出荷のピークを迎えますが、新米が8月13日にはもう出回ってもいるのです。
この中で、備前焼をピックアップして見るとどのようなことが分かってくるでしょうか。
伊部・片上港の場合はたいていは米、大麦、小麦、苧、マメ、ソバ、ゴマとツホ(壷)、すなわち備前焼が混載になっています。それはこの地が農業地帯でもあり、半農半窯だったこともうかがわせています。
中でも苧、つまり麻は瀬戸内第一の特産であったようですし、記録上に頻繁に登場することと、税金も高いことなどからこの様子だと金額的にもかなり稼いでいたようです。
港に陸揚げされた備前焼点数は一年間で1,075個に及び、実に日本の中心であった当時の京畿に流入する全焼物の85パーセントを備前焼が占めている勘定になります。完全なる市場制覇が行われていたことが文書からも裏付けられました。
またこの表から、当時は季節的に輸送量がかなり偏っていることが分かります。現在では殆ど年間を通じて備前焼は生産されているのに、かつては何故季節的制約を受けたのでしょうか。