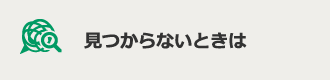本文
備前焼の生い立ち(1/7)
《 引 用 文 献 》 「備前焼の伝統と歴史(備前焼の歴史と文化)」 臼井洋輔著・岡山県備前焼陶友会
備前焼の前身・須恵器のはじまり
焼物の新しい時代
縄文式土器、弥生式土器の時代を経て、5世紀頃の日本には、新しい時代が外からやってきました。ロクロの導入、野焼きから一転して、窯の築造とそこからくる、一層の高温を維持する焼成技法などを携えた「須恵器」の到来です。
日本各地に、頑丈で水の漏らない須恵器を焼く窯が渇望されて瞬く間に広がっていきました。この備前の地でも、盛んに焼かれました。邑久郡一帯で焼造された、備前焼の前身の古代の寒風窯の製品は、朝廷に調(税金)として納めるモノであった性格上、ロクロを使い非常に端正で美しく、可能な限り白く、それはまた中国の焼物に出来るだけ近づけようと指向し、努力することから始まった焼物でした。当時価値のある陶磁器とは中国の玉のように美しく、端正なものを指していました。それを持つことは特権階級の者にとって、一つのステイタスシンボルでありました。
その様な中で、東海の雄猿投窯とともに、暗灰色の他のこれまでの須恵器よりはるかに白く、硬く、その上美しい薄緑色の自然釉の衣装をまとったものが生まれ、日本の二大勢力をなしていきました。この一方が、飛鳥〜奈良時代にかけて活躍した寒風窯であり、それに沿った寒風窯は深く深く律令制の中に組み込まれていったのです。これが備前焼のルーツです。
貞観13(871)年『貞観式』にも備前国からの須恵器貢納の記述があらわれています。律令制に深く根ざし、一大生産地となり他に先んじて窯印さえすでに多用して、断然高いレベルと美しさを誇るものでした。出土物からみても、大寺院の鴟尾、大壷など巨大なものも非常に得意とするところでありました。
またこの頃の寒風の作品が、このように大きさと、質の点で群を抜いていたかということは、牛窓町民俗文化資料館、備前長船博物館、山手村の吉備考古館の関係資料を見れば、誰でも往時をしのぶことができ、またその心意気もうなづけるはずです。
平安時代の備前焼
厳しい冬への時代
延喜5(905)年の『延喜式』の記載によれば、須恵器貢納国の中では備前国が最も生産量が多いことが分かり、平安時代もさらに勢力を拡大していたことが分かります。
備前焼大甕(一石程の容量でややタテ長で、すべて口縁は玉縁ではなく、平たく大きく外反している)が京の都まで運ばれて町屋などでもすでに用いられていたことが、京都大学資料館等にある出土品からもよく分かります。しかしその後平安時代も終わりに近づくと、中央集権体制のタガが緩み、律令制が崩壊する過程で、中央はすべてが混沌としていったのです。
そうした状況下で焼物は、祭器や一部の貴族だけのものではなく、庶民の暮しの道具として需要が拡大していきます。このように古代末には新しい時代の到来を告げる序曲が始まっていたのです。
古代律令体制が崩壊し、あちこちの地方から政治や経済の新しい波が起こり、それに呼応して東海の雄猿投窯はすぐ渥美、常滑、瀬戸へと分裂して新し道を切り開きました。
日本の社会で初めて、焼物を庶民が庶民のものを庶民のために作り、「商品として流通」させた中世という全く新しい時代が始まろうとしたのです。初めは、余剰物を商う程度から始まりましたが、日本の歴史の中で初めて庶民が表舞台に登場しました。この輝く新しい時代の流れはもう誰にも止められませんでした。
このとき、また他の全国の新生中世古窯も一斉に開花し、それぞれ大発展を遂げました。そうなると全国各地の窯は次第に、一般向けの商品として焼くことが出来るように大型化し、整理されて、全国にいくつかの「産地」というものが誕生してきました。
それに対して、古代の寒風窯の時代から律令体制の中に強く組み込まれて繁栄し、一大窯業地として確立していた備前は、本来の力はありながら律令制の崩壊という事態で受けた打撃が余程大きかったらしく、他の中世古窯が快進撃をする中で、焼物の表情にまだ明るい美しさも出せず、時代が変わる中で窯場の場所もふらふらして定まらず、生産規模でも比較になりませんでした。
そのことは焼物の表情にもはっきりと表れています。都から遥か遠く離れていた渥美焼とか常滑焼の他の古窯は庶民の時代を迎えると、既成のものにとらわれず、酸化焼成の赤い発色を確立し、大変な自信と勢いと明るさを持って堂々とした作風になっていたのに対し、備前はまだ灰白色のままであったし、製品の勢いも失せ、新旧の間をさまよい、自信喪失の有様がよく表れています。
こうしてモノの力や表情のみならず、量からみても渥美、常滑などの快走と拡大に比べ備前の窯業は皮肉にも大きく後退を余儀なくされ、厳しい冬の時代を迎え、耐えねばなりませんでした。その頃の備前は邑久町の磯上などが主要な窯場でした。