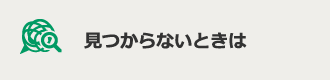本文
備前焼の生い立ち(6/7)
細工物で再興を
備前焼の新しい方向が打ち出されます。元和5(1619)年に備前透文釣燈篭銘「元和5年 木村二郎介卯月吉日」に現れ、細工物の年銘物初出を知らせています。この細工物こそ藩の備前焼再興指導の中心になるものであったのです。
寛永9(1632)年には池田光政岡山藩主となり、次々と備前焼に介入していきました。
寛永13(1636)年、与八と新五郎の名工細工人を任命し、それぞれ扶持米9斗6升を給しました。幕末までこの人間国宝にも当たる制度は藩の産業振興の一環として続けられました。御細工人制度は、名産としての備前振興のため強い指導と規制を加えるのですが、かえって作品は画一化、硬直化の道をたどることになります。
貞享4(1687)年に閑谷村の土で、閑谷学校瓦が焼かれます。この頃閑谷瓦窯において、閑谷の土で焼いた焼物である閑谷焼が始まるのです。もちろん閑谷焼の文献的初出です。元禄4(1691)年伊部焼物に、ヘラ目の使用を禁止するとの藩の指令がなされ、販売のみならず、技法まで藩の意向が反映されていることが分かり、硬直化は極に達します。
元禄7(1694)年「焼物諸事蔵法書」に、閑谷焼釉薬の調合法が記載されております。かなり科学的に研究し、藩内の産業にしようとしたのかも知れません。しかしその後の動きを見れば、結局備前焼の伝統はそれを拒否したことになります。元禄13(1700)年備前瓦銘に「元禄十三庚辰年終秋上五日 閑谷 御學校講堂瓦 磯上……」藩主導のもとに備前焼瓦が作られています。瓦は美術作品と違って工業規格的なものが要求されたはずです。そういった新しく始める物はやはり藩主導になったのでしょう。今日の産業のあり方と少しも変わりません。
宝永3(1706)年には京・大阪へ伊部焼物行商を願い出ています。しかし宝永4(1707)年には藩は江戸・大阪への備前焼行商を禁じています。中世のようなあの自由闊達な商品経済は夢のまた夢で、経済の法則からは、いくら新しいものを藩が試みても歪んだものとなっていました。
彩色備前、白備前、青備前も
宝永7(1710)年には御細工人木村長十郎が、白焼研究のために、肥前に行っています。もちろん藩の許可のもとに行ったのです。藩の主導のもとに貞享4(1687)年の閑谷焼開窯、正徳元(1711)年の白備前、正徳4(1714)年の彩色備前と新機軸が次々と打ち出されました。享保5(1716)年北窯組合9人から、不景気を理由に大窯を3分の2に縮小したい旨を藩へ申し出ていますが、これは経営形態まで藩に握られていることを示していることに他なりません。
伊部焼燃料は秀吉以来無料で払い下げられていましたが、享保年間に有料になったので、享保10(1725)年無料払い下げを願い出て、山役代のみ有料として許可されました。窮状に対しては、公定歩合のコントロールのように酌量していたのです。享保15(1730)年には狩野自宣が伊部焼物御用を仰付けられています。備前焼に本格的に彩色することを企てたのです。享保15(1730)年になると藩の絵師が三十六歌仙等の色彩備前を制作しています。これは今日の博多人形のように甘い焼の素地に顔彩や岩絵の具を膠を使って彩色したものです。
天保13(1842)年西大窯はさらに困窮のため北大窯にならい三尺床を埋めて容量を少なくして規模縮小をしたいと願い出ます。備前焼が藩の打開策の模索にもかかわらず次第に窮乏していった様子がうかがわれます。こうした支配が備前焼のために良かったのか否かは、時代というものを考えると難しいところです。
ともあれ備前焼の、新時代に適応した新しい造形美は大まかに「伊部手」、「細工物」、「彩色備前」、「白備前、青備前」などとバリエーションを増していきました。
「伊部手」は磁器の肌理の細かさを陶器で実現し、時に金属的光沢を求めた工芸美を意識したシャープな様式であり、「細工物」は福の神や人物、狛犬、鳥獣など、置物や香炉として作られました。また陶工を有田にまで勉強に行かせて、あくまでも備前の土で白いものを作ろうとしたのが「白備前」です。「青備前」は食塩を使って発色させるなど、焼成技術で改革を加えたものです。また顔彩や岩絵の具をほどこした「彩色備前」は困窮の中でも異彩を放っています。
池田藩はわが国で最初期の青磁や藩窯品としての閑谷焼など各種の変わり種備前を大いに奨励し、また窯元六姓を定め、備前焼の保護育成を行ってはみたのですが、所詮退潮の時代的流れを食い止めることはできませんでした。これが種類や表現で非常に多くの備前焼を生んだ江戸時代の背景でもあります。総じてこれは対症療法的やり方ともいえ、換言すればあがきの証でもあります。