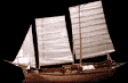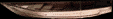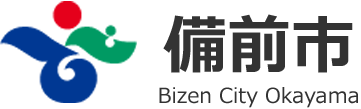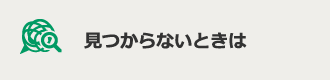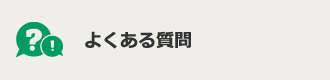本文
加子浦歴史文化館・資料館
資料館

資料館では、“海と共に生きるまち”をメインテーマに歴史や産業のあゆみを、各テーマごとに展示しています。土器や竪穴・高床式住居の模型を展示した出土品のコーナーや絵図・民具などが興味深い歴史のコーナー、また海のまちらしく弁財船、打瀬船の模型や船舶用具などを展示した漁業や海運関係のコーナーなどを設けて、まちの歴史や海とのかかわりを総合的にわかりやすく紹介しています。また建物自体も日生町内の吉田家を移築、再現した造りになっており、見応え十分です。
【下の図で見たいブースをクリックしてください】
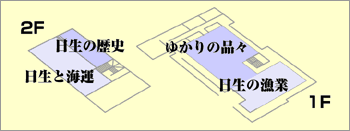
資料館の学習室、茶室および文芸館の市民ギャラリーは一般利用(有料)できます。
日生の歴史

資料館では、“海と共に生きるまち”をメインテーマに歴史や産業のあゆみを、各テーマごとに展示しています。土器や竪穴・高床式住居の模型を展示した出土品のコーナーや絵図・民具などが興味深い歴史のコーナー、また海のまちらしく弁財船、打瀬船の模型や船舶用具などを展示した漁業や海運関係のコーナーなどを設けて、まちの歴史や海とのかかわりを総合的にわかりやすく紹介しています。また建物自体も日生町内の吉田家を移築、再現した造りになっており、見応え十分です。
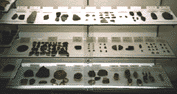
日生は瀬戸内海に面し、多くの島々から成り立っている。陥没して出来たこれら島々の海は、魚の絶好の魚礁となり、島々に囲まれたリアス式の海岸は寒河・日生に天然の良港をもたらせた。そして人々は縄文・弥生の昔から狩猟・漁労で生業をたてていた。
平城京から出土した710年の後半といわれる日生からの木簡も、恐らく日生の魚を税として納めた荷札であろうと言われている。また室町時代中頃に、日生からナマコを積んだ船が二艘兵庫の北関に寄った記録があり、近隣に売るだけでなく京・大阪にまで魚を売るほど漁業の村として発展していたわけです。
江戸時代の初めには日生・寒河で約500石の米が取れていたのだから、百姓と兼業で魚を獲っていたのであろう。当時は灘、虫明布浜から室津、小豆島中海までの日生近海が漁場であったが、江戸末期には近海での魚の減少から、サワラ漁の流瀬船が阿波・讃岐・淡路・播磨まで300隻も出漁するようになった。そして日生船のとったサワラは、大阪魚市場で「魚島サワラ」と呼ばれ、非常な高値で取引きされた。
日生の漁業


明治になると愛媛四阪島から三田尻、大分、福岡、また徳島、和歌山、伊勢湾迄出漁した。日生に魚市場を作り、日生漁業組合を結成して新時代に即応した漁業の展開を図ったが、「漁業法」の施行により他県の漁場が制限されたことと、魚の減少で、目を海外に向けることとなる。
朝鮮には明治20年に川崎甚平・甚九郎兄弟が、続いて戸長真殿伊治が120人を率いてと、朝鮮出漁は盛んとなり、絶影島、方魚津、浦項、筏橋、羅老島に根拠地をつくり、やがてその地へ定住した。魚を獲るだけでなく、魚の加工や雑貨屋、漁具、洗濯屋、電気屋を始めた者も出た。中には金谷一二・大介兄弟のように精米業から農場経営に、満州だけでも2000町歩の農地を持つ迄になった人もいる。朝鮮漁業初期には、鮮魚の日本への運搬のため仲買い組合を作ったり、林兼(大洋漁業の前身)と共同で魚の運搬に従事する人々も出た。朝鮮で彼等は、「共に人間」と共存協栄をはかり、融和の中で発展を図った。



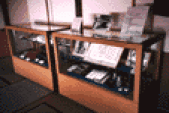
太平洋戦争終結後の朝鮮引揚者は、501人と言う多数に上ったが、混乱を極める中日生引揚者の多くは、家屋敷・家具等を使用人に与え、朝鮮の人が「帰るな、帰るな」と涙を流して別れを惜しんだという状況であった。また戦後朝鮮引揚者が、第二の故郷の韓国訪問団を組織し訪韓した時、家族が再会した如く抱きついて喜んだ。ということに日生人らしい心の広さ・温かさ、協調性が見られ、また常に新しい事業に挑戦しようとする進取の気性がこの朝鮮漁業に良く表れていると言えよう。また海外進出は、朝鮮の他に、大連、台湾、マニラ、シンガポールと100人以上の人々により行なわれ、世界への夢を実現させていたのだ。
海外漁場を失い、国内漁場の制約の厳しくなった戦後は、漁業協同組合や魚市場の立て直し、養殖漁業への進出を図った。漁協に婦人部、青年部を創設し後継者の育成をはかり、「浜売り」で生産者と消費者の直結を考え、共同出荷で大阪・東京の市場に進出し新鮮で安価な日生の魚の提供をと、常に他に先駆けて日生漁業の発展を図った。養殖漁業は片岡松吉氏が提唱し、昭和32年現寺湾でのハマチ養殖をきっかけに、車エビ・ノリ・カキ等の養殖に積極的に取り組んで教科書にも取り上げられた。北洋のサケ・マス漁にも専用船を組合で建造し新漁場開拓にと、日生の漁業は先人の英知を受け継ぎ戦前の真殿伊治・吉形忠治、戦後は有吉敏治・岸本辰夫・坪本正一等代々の指導者の素晴らしい先見性と指導力のもとにさらなる発展を続けている。
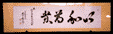

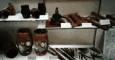
日生の漁業は、近海・内海・遠洋とに分けられ、漁法はサワラ流瀬網・打瀬網・坪網・大網、タコ縄・繰り網・建て網・イカ網、それに一本釣りがある。特に日生最古の漁法と伝える打瀬網、日生の考案の坪網、江戸中期以降日生流瀬として著名な流瀬網が主流で、有名である。この他現在取り組んでいる栽培漁業は新しい漁業形態であり、大きな発展が期待できる。
漁業は、古くから日生人の生業の基盤であり、人々は小船に命を預け日々を過ごしてきた。そして船泊りで常に国内や海外情報をつかんだ人々は、いつも目を外に向け、勇壮で、明るく、進取の気性に満ちていた。郷里を愛し、生きものを愛し、慈愛に満ちた広い心を持っていた。古くから遠き京を相手に魚を売り、日生独自の「つぼ網」漁法を発明し、いち早く朝鮮を始めフィリピン・シンガポールへと海外へ進出。そこに定住し、二次大戦後漁獲が少なくなれば「養殖漁業」を開拓、更に「栽培漁業」にと、常に時代の先端を行く、先進的な漁業の町である。