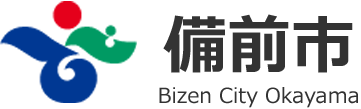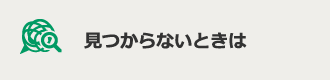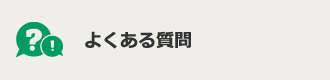本文
加子浦歴史文化館・文芸館
文芸館

昔の蔵をイメージした造りになっている文芸館では、日生町で生まれ育った人々で、郷土の誇りである人物を紹介しています。小説家として活躍した里村欣三、文学者である牧野大誓、画家の久保田耕民を中心とする「日生ゆかりの人々」の作品や遺品を展示しています。多感な少年時代を日生町で過ごし、現在作曲家として活躍中の岡千秋さんのコーナーもお見逃しなく。
【下の図で見たいブースをクリックしてください】
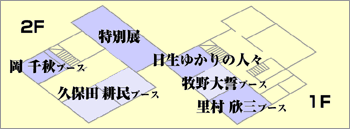
資料館の学習室、茶室および文芸館の市民ギャラリーは一般利用(有料)できます。
岡 千秋
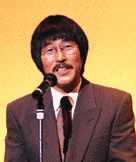
岡千秋
日生町(鴻島)出身の作曲家。レコード大賞受賞をはじめ、各音楽賞のビッグタイトルを数多く受賞。


牧野大誓
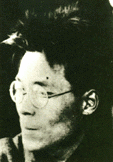
牧野大誓
1894-1967
児童文学者。備前市日生町(旧日生村)生まれ。朝日新聞懸賞募集の少年少女映画ストーリーに「二つの玉」を応募し、入選、松竹で映画化される。「長靴の三銃士」がベストセラーになり「へのへの竜騎士」「くえびこ様」などを発表し、講談社から刊行した。
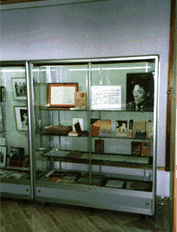
里村欣三

里村欣三
1902-1945
小説家。備前市日生町(旧福河村)生まれ。1923年徴兵忌避、逃亡、満州に渡り放浪生活を送った。帰国してプロレタリア作家として活躍。その後、中国、マレーシア、ボルネオ方面に従軍、従軍作家として名声を得たが、フィリピンで戦死。「苦力頭の表情」「第二の人生」「兵の道」「熱風」「河の民」などの作品がある。
戦争中、報道班員としてマレー方面に里村と共に派遣された文学者の堺誠一郎をはじめ、小説家の井伏鱒二、海音寺潮五郎、神保光太郎のほか写真家で有名な石井幸之助などの作品を展示しています。その中には、数多く里村が書かれたものがあり、往時の交友関係が忍ばれます。

久保田耕民
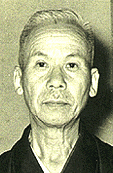
久保田耕民
1890-1969
南画家。備前市日生町(旧日生町)生まれ。郵便局に勤めるかたわら大阪美術学校に学び、永松春洋に師事して、南画を学ぶ。号を香雲、香芸と称した。
「秋塘」が帝展に入選。号を耕民と改めた。大阪画家協会を設立するとともに、日本南画協会理事、大阪有秋会会長として後輩の指導に当った。
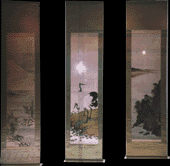
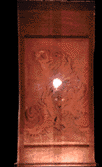
「正宗白鳥」(1879〜1962)
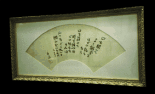
明治から昭和にかけての日本を代表する文学者。早稲田大学を出て、島村抱月の指導で評論を書き始め1903年読売新聞社入社。記者生活の傍ら小説を書き始めて、「塵埃」、「何処へ」で自然主義作家として認められた。然し彼の本領は評論であり文芸時評や回想録等に優れたものがある。子供時代や帰郷の時、日生の風光を愛でて日生に訪れたという。岡山県備前市伊里出身。
直木賞作家
「藤原審爾」(1921〜1984)

備前市(旧片上町)で生まれ、閑谷中学から青山学院に進んだが病気のため中退し岡山市に疎開。文学を志し、同人誌「曙」を引継ぎ発行。文学界に発表した「練る煉獄の曲」で認められ、奥津温泉をテーマにした「秋津温泉」が出世作となった。昭和27年「罪な女」で「直木賞」受賞。社会的テーマを追い時代小説・推理小説も書き、作品は多数。日生には魚と風光を求めて良く来訪。日生の甚九郎の小説を書くこと、日生に別荘を建てたい等の話が具体化しているとき、死去。
作家「眉村卓」(1934〜

大阪出身の小説家、本名は村上卓児。大阪窯耐に就職、日生工場に昭和32年から11ヶ月間勤務す。同33年から大阪に転勤になり、同38年の9月に大阪窯耐を退社す。彼は此の日生勤務を、
「日生には11ヶ月足らずだったが、大阪生れの大阪育ちで、初めての異郷暮らしだったし、疾風怒涛の時代であった。……小さい頃住んでいた場所が空襲で焼かれ、…日生になんとなく故郷めいたイメージを抱くようになった……その後も、仕事が行きづまったり、ストレスがたまってきたりすると、日生へ出掛け、一泊する癖がついた。今でもそうなのである。
実をいうと、ぼくは、そのせいで、自分の書いたものの舞台に、何度も日生を使っている。……」
日生に来た最初の夜錦水に泊り、日生に居る間よく飲みに行ったらしい。また寮でも良く飲んでいたということだ。
文学に関心の強かった彼は、勤務の傍ら詩や俳句を作り続け、同36年に、Sf中間小説「下級アイデアマン」で文壇に登場す。会社をやめて小説家として独立、昭和54年「消滅の光輪」で「泉鏡花賞」を受賞する。純Sf的な味わいの中・短編小説で知られている。
特別展
さまざまな展示を行います。(催し物のごあんないへ)