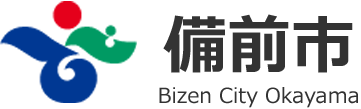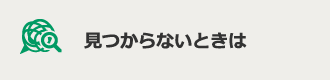本文
e-Bizen Museum <柴田錬三郎略伝5>
柴田錬三郎略伝
東鶴山公民館
錬三郎の少年時代
大正12年4月、柴田錬三郎は鶴山尋常小学校に入学する。小学校は瀬戸内海の入江の奥にあった。

始業を報じる板木(ばんぎ)がなりひびく。1時間目は国語だ。教師が黒板に大きな文字でかたかなを書いてゆく。それを実竹の棒の先で一語一語さし示しながら、生徒らに復誦させる。
錬三郎は小学校1年生にして、小学校で習うくらいの漢字は読み書きできたので、こと国語の時間は退屈だった。
幼いころから、錬三郎は父親が書屋にのこしていった漢籍を眺めるのが好きだった。なんとはなしに、漢文の格調に惹れつつ育っていたのである。
だからといって、錬三郎はすこしも勉強はしなかった。いつも、小さな青大将を飼いならして、着物の袖に入れているような少年だった。
錬三郎は毎日、くたくたになるまで遊んだ。夏は海水浴だった。家の前の県道をたどって行くと海へ出る。錬三郎は毎夏この道を歩いて、海水浴へ行った。村の母親たちは、子どもらが浜辺で遊ぶことをすこしも心配していなかった。瀬戸内海べりの入江の海は、湖のようで、砂をあらったり岩をたたいたりする波はなかったからだ。錬三郎は小学校へあがる前から、泳ぎが上手であった。
錬三郎の小学校時代のいたずらは、みな型破りだった。たとえば――。
ある日、隣村から花嫁が輿入れをした。当時の風習として、向こう三軒両隣りへ、花嫁は挨拶まわりをしなければならない。あでやかな花嫁衣裳の姿に、つのかくしの顔をうつ向けて、文字通り虫も殺さぬ、しおらし気な顔で、花嫁御寮はしずしずと歩いていた。
それをじっと見つめていた錬三郎の脳裡に、ふと奇抜なアイデアが湧く。錬三郎はすぐちかくにあった竹竿を手にとるや、いきなり背後から、花嫁の裳裾をぱっとはぐり上げたのだ。瞬間、ふり向いて、錬三郎)をにらみ据えた花嫁御寮の形相は、まさしく華厳経に説くところの「女人は地獄の使い」そのものであったという。
またひとつ。
鶏が鳥のくせに空も飛べずに、卵ばかりを生んで人間に奉仕しているのが、なんとなく面白くなかった。空を飛べないのなら、せめてアヒルのように泳がせてやろうと考えたのだ。
錬三郎は隣家の鶏小屋から、5、6羽ぬすみ出して、これをじゅずつなぎにして、海辺までひっぱって行く。そして、小船を漕ぎ出して鶏を海面へはなしたのだ。鶏たちは敢えなくも、のこらず溺れ死んでしまった。ざっとこんなあんばいである。
腕白だった錬三郎は、しばしば母親から灸をすえられた。教師にも殴られた。その腕白ぶりに、各戸から猛烈な抗議を受けることもあった。そのたびに、母親はあやまりにまわらなければならなかった。
母松重は、もはや自分にはお前のような悪童を育てる気力が尽きたと、泪ながらにかきくどいた。学校の勉強などどうでもいいから、いたずらをやめてもらいたい、とひたすら錬三郎を諌めるのだった。
柴田錬三郎は、みずからこう洩らす。「自分は、故郷の岡山の海辺の村はじまって以来の腕白小僧であった」と。
たしかに錬三郎のいたずらは、度がすぎていた。母親がやりきれなかったのもわかる。だが、そのいたずらは、自分なりに意義をもっていたのである。
錬三郎は探究心の旺盛な少年だった。腑に落ちぬことには、がまんがならなかった。疑問をいだけば徹底的に納得のいくまでやってみたかった。
ただ、2歳上の次兄大史郎(だいしろう)が、学術優秀、操行甲(そうこうこう)の模範生であっただけに、錬三郎の行動は悪童の典型として大人たちの目に映ったのである。
松重はごく平凡な、何処にでもいるような女性であったのだろう。すくなくとも、息子の行動に対して、お節介をやいたり口をさしはさむ現代の教育ママ的存在ではなかったはずだ。だが、残念なことに、松重は錬三郎の直木賞受賞を知らない。受賞する半年前の昭和26年に鬼籍に入っている。
忙しかった母松重に代わって、錬三郎の面倒をみてくれたのは祖母であった。備前藩の武家の娘として育った祖母は、何事においても慎ましかった。
祖母は、3人兄弟中、もっとも錬三郎を可愛がった。父親を早くに亡くし、母親は忙しかったから、ことさら錬三郎を哀れんでいたのかも知れない。哀れみは深い愛情にかわる。末っ子を溺愛する祖母。錬三郎も祖母には甘えた。けれども、その甘え方には、お婆ちゃん子にみられる軟弱さはない。
錬三郎が小学生のころだ。
小遣いが足りなくなれば、錬三郎は祖母を恃(たの)みとする。恃みとしても、ただ、くれとは言わない。まことしやかな理由をつけて小遣いをせしめる。だが、毎度同じ嘘はつかない。話はだんだん巧妙になってくる。
祖母は嘘を看破していた。それでいながら一度もたしなめたことはなかった。いかにも、錬三郎のつく嘘を、本当のことのように笑顔できいていた。祖母はだまされたふりをして、いつも小遣いをあたえていたのだ。