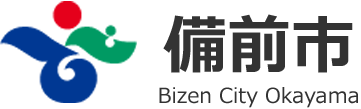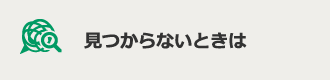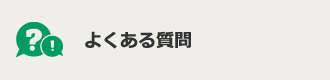本文
e-Bizen Museum <柴田錬三郎略伝4>
柴田錬三郎略伝
東鶴山公民館
錬三郎の生い立ち
柴田家は錬三郎の祖父の代から、備前地方の典型的な 中地主であった。父柴田知太(しばた ともた)は婿養子だった。長女松重と結婚して中地主の家を継いだのである。
同時に、知太は鏑木清方と同門の日本画家でもあった。しかし、柴田知太は 早世した。錬三郎が3歳の時に亡くなっている。だから父親の面影を偲ぶこともなく育ったことになる。父親については唯一こう記しているだけである。
私の亡父は、無名の日本画家で、多芸多能であったが、ひとつとして成らずに、終わった。ただ多少の漢籍を書屋に、多少の資質を倅の血のこして行った。
(『眠狂四郎無頼控百話・下巻』覚書、昭34.8新潮社刊)
柴田知太はしょせん趣味人にすぎなかったのだろうか。ちがうとおもう。かれが描いた1枚の絵を観かぎり、趣味の域はこえている。ただ、中央画壇から遠くはなれた岡山の田舎で画筆だけをふるうことは、むつかしいことであっただろう。いや、むつかしいというより、柴田知太は日本画家として大成すること以上に、家長としての責任を重んじる常識人だったとおもう。
錬三郎の血中には、そんな父親の芸術を志向する資質もさることながら、律儀な面ものこされていたのである。
錬三郎には2人の兄がいた。
長兄柴田劒太郎(しばた けんたろう)は、錬三郎よりひとまわり上だった。昭和4年、劒太郎は大学卒業後、朝日新聞社に入社した。錬三郎が中学校へ入学した時である。父親を早く亡くした錬三郎にとって長兄と劒太郎は兄というより親父みたいな煙たい存在だった。錬三郎はよく小言を言われた。
柴田劒太郎は大学生のころから文章を能くした。朝日新聞社に入社後、記者時代を経て、整理部次長、写真部長、福岡総局長、論説委員を歴任したが、仕事の傍小説や随筆を書き、数冊の著作がある。